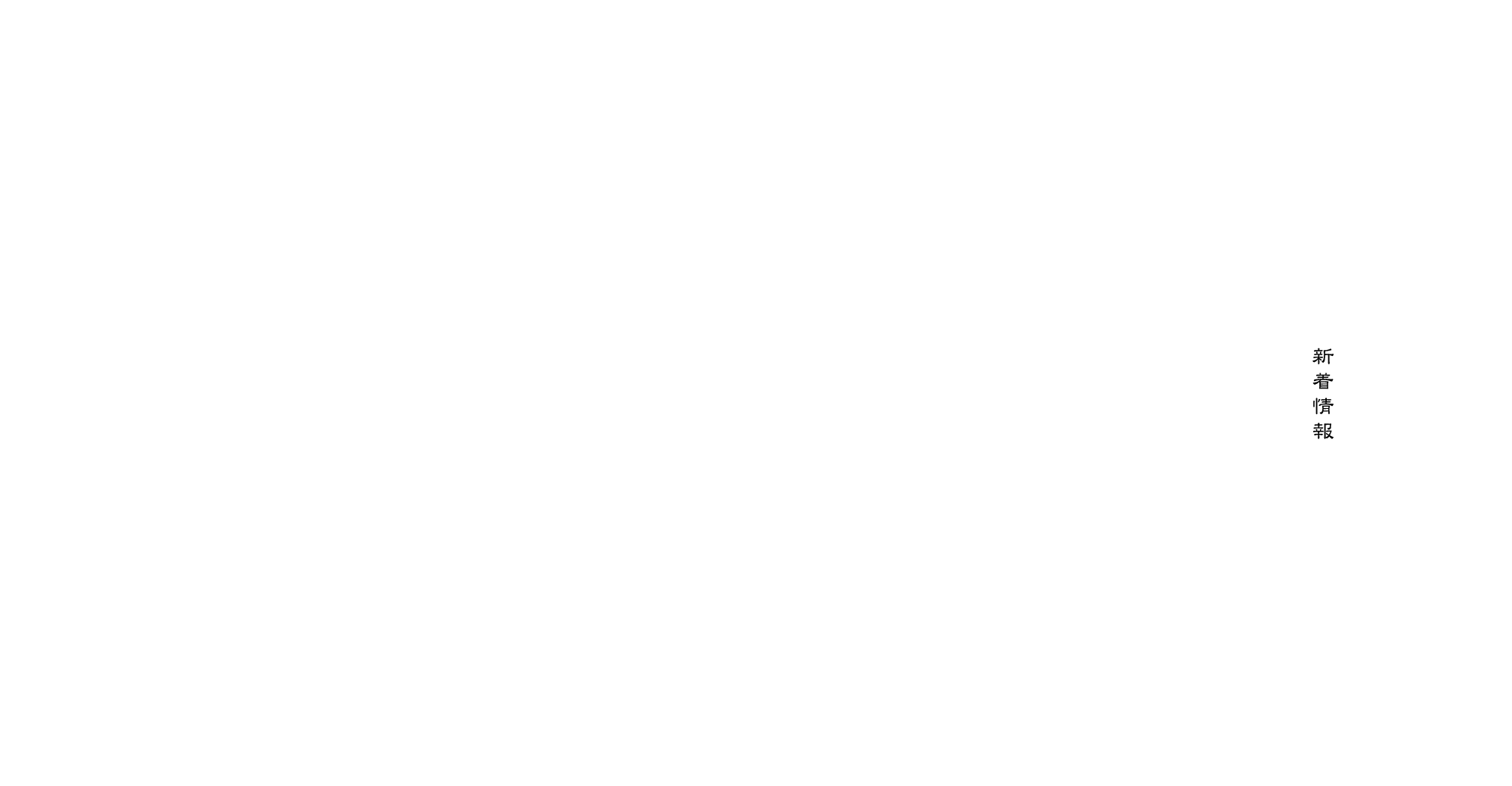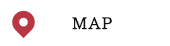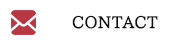皆さんこんにちは!
矢尾定の更新担当の中西です。
さて今回は
~立冬を迎えて~
11月上旬、暦の上では立冬。
この頃になると、京都の料理人たちは“冬の支度”を始めます。
素材は脂を増し、野菜は甘みを蓄える──そんな自然の変化を、京料理では「出汁」で受け止めます。
1. 出汁文化の真髄
京料理の根幹は、なんといっても“出汁”です。
鰹節と昆布、それに追い鰹。透明で、香り高く、旨味が重なる。
この出汁があるからこそ、淡い味付けでも心に残る余韻を生むのです。
11月になると、水温が下がり、昆布の旨味が最も引き出される季節に。
職人たちは、火加減と時間を調整し、温度計を使わずに“香りと気泡の表情”で仕上げる──まさに経験と感性の世界です。
2. 出汁が決める冬の献立
冬の炊き合わせ、湯豆腐、葛仕立てのお椀。
いずれも出汁の質が味を左右します。
たとえば聖護院大根の炊き合わせは、優しい旨味を染み込ませるために、一晩寝かせてから仕上げるのが京風。
「急がないこと」が美味しさの条件なのです🍲。
3. 仕出しにおける“温もりの工夫”
仕出し料理は持ち帰り・配達が前提。
そのため温度管理と香り保持がとても難しい。
保温性の高い二重折箱や、出汁ゼリーを使って香りを閉じ込める工夫が進んでいます。
「冷めてもおいしい」ことは、出汁文化の成熟を示す指標でもあります。
4. 出汁は“もてなしの心”
出汁は、料理人の心の鏡。
派手さはないけれど、誰もが「ほっとする味」。
それが京都人の“おもてなしの本質”です。
11月、立冬を迎えて、温かい一椀を手にする瞬間。
湯気の中に香る出汁は、冬を迎える京都の心そのものです🌾。
献立はこちら