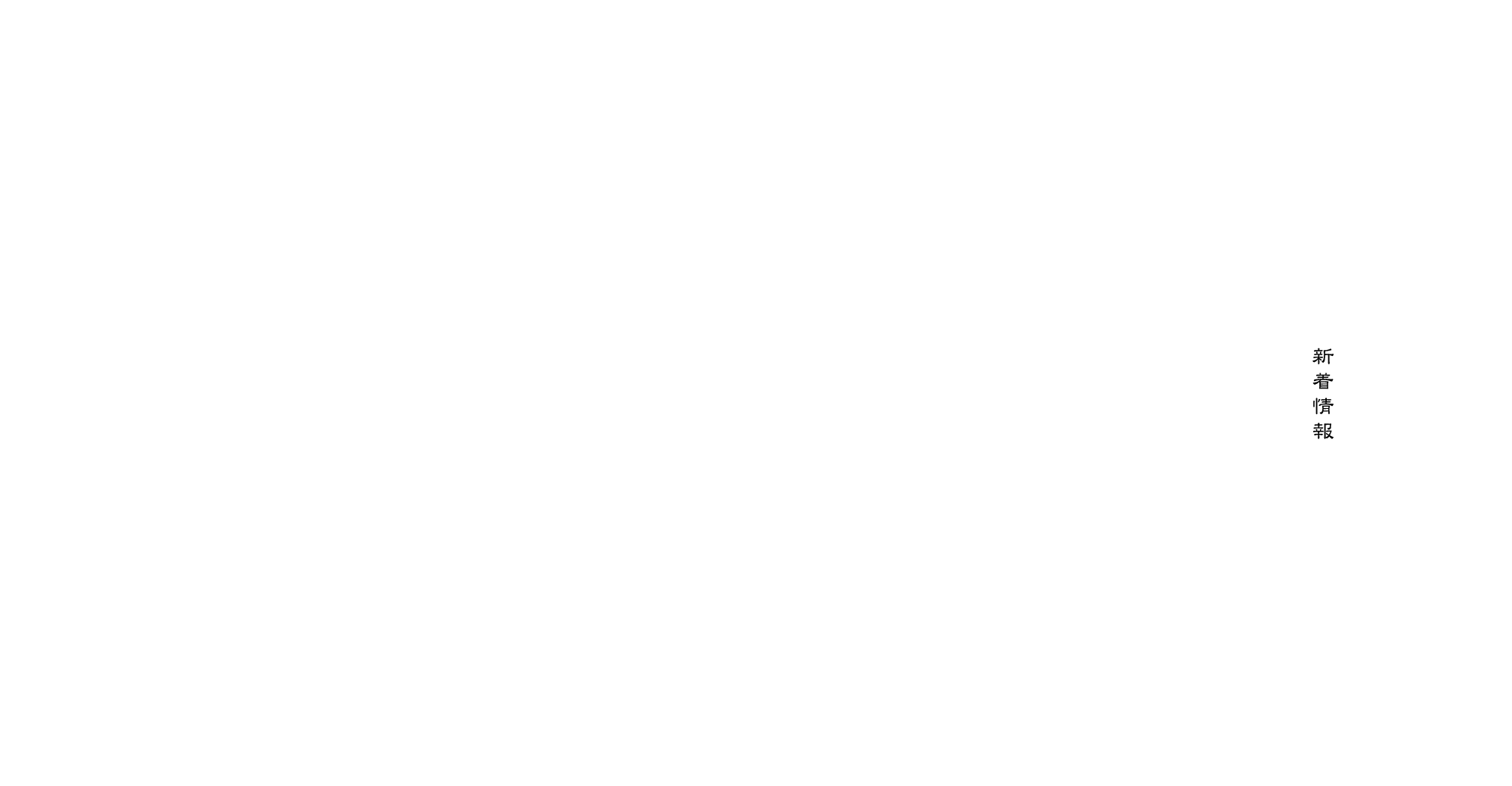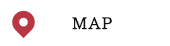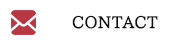皆さんこんにちは!
矢尾定の更新担当の中西です。
さて今回は
~雅を運ぶ料理~
1. 仕出しとは
「仕出し」とは、本来「料理を作って運ぶこと」を意味します。
現代では“仕出し弁当”という言葉がよく使われますが、京都の仕出しは単なる弁当配達とは一線を画します。
そこには「おもてなしの心をそのまま届ける」という発想があり、料理はもちろん、器や盛り付け、香り、さらには季節感まで運ぶのが特徴です。
2. 京都仕出しの起源
京都における仕出し文化は、室町時代〜安土桃山時代にさかのぼります。
当時の京都は天皇や公家、武家、寺社が集まる政治・文化の中心地。茶道や華道といった「もてなしの芸術」が発達し、食事も儀式の一部として位置づけられていました。
もともと貴族や武家の屋敷では、来客時に料理を自宅で用意するのが常でしたが、大規模な宴会や儀式になると、料亭や料理屋が出向いて料理を用意するケースが増加。
これが「仕出す」=料理を作って外へ運ぶという形に発展しました。
3. 江戸時代の発展
江戸時代に入ると、京都の町には数多くの料亭や仕出し専門店が誕生しました。
公家や大名の屋敷では節句や年中行事のたびに盛大な宴が開かれ、そこへ仕出しが利用されます。
さらに、町人文化が花開くと、商家でも結納・祭礼・法事などハレの日の食事として仕出しが広く浸透しました。
この頃の京都仕出しは、料理だけでなく器や飾りつけも持ち込み、食後に引き上げるのが基本。
まさに「料亭がそのまま家にやってくる」ようなサービスだったのです。
4. 文化的背景と京都らしさ
京都の仕出し文化が特別なのは、以下の要素が組み合わさっているからです。
-
四季の美意識
桜の花びらをかたどったかまぼこ、紅葉の形をした人参、冬には雪を思わせる白いあしらい見た目から季節を感じさせる盛り付けが徹底されています。
-
京料理の流れ
薄味ながら奥深い出汁文化、素材の持ち味を生かす調理法がベース。見た目の華やかさと繊細な味が共存。
-
行事との結びつき
茶会、節句、祭礼、法事など、日本の年中行事と密接に関わり、その場にふさわしい献立や器を選び抜きます。
5. 明治〜現代への移行
明治以降、交通網が発達し、仕出しはより広範囲に提供できるようになりました。
昭和になると折詰弁当が普及し、冠婚葬祭や会社の会議弁当にも使われるように。
しかし京都では、いまなお「料理を通して文化を届ける」という精神が守られ、料亭や老舗の仕出し店が地域行事や寺社祭礼を支えています。
京都の仕出しは、単なる料理配達ではなく、
歴史・美意識・季節感・儀礼を一緒に届ける文化です。
その背景には、千年の都で育まれた「雅の心」があり、今も変わらず人と人をつなぐ役割を果たしています。
これこそが、京都仕出しが時代を超えて愛され続ける理由なのです。
献立はこちら