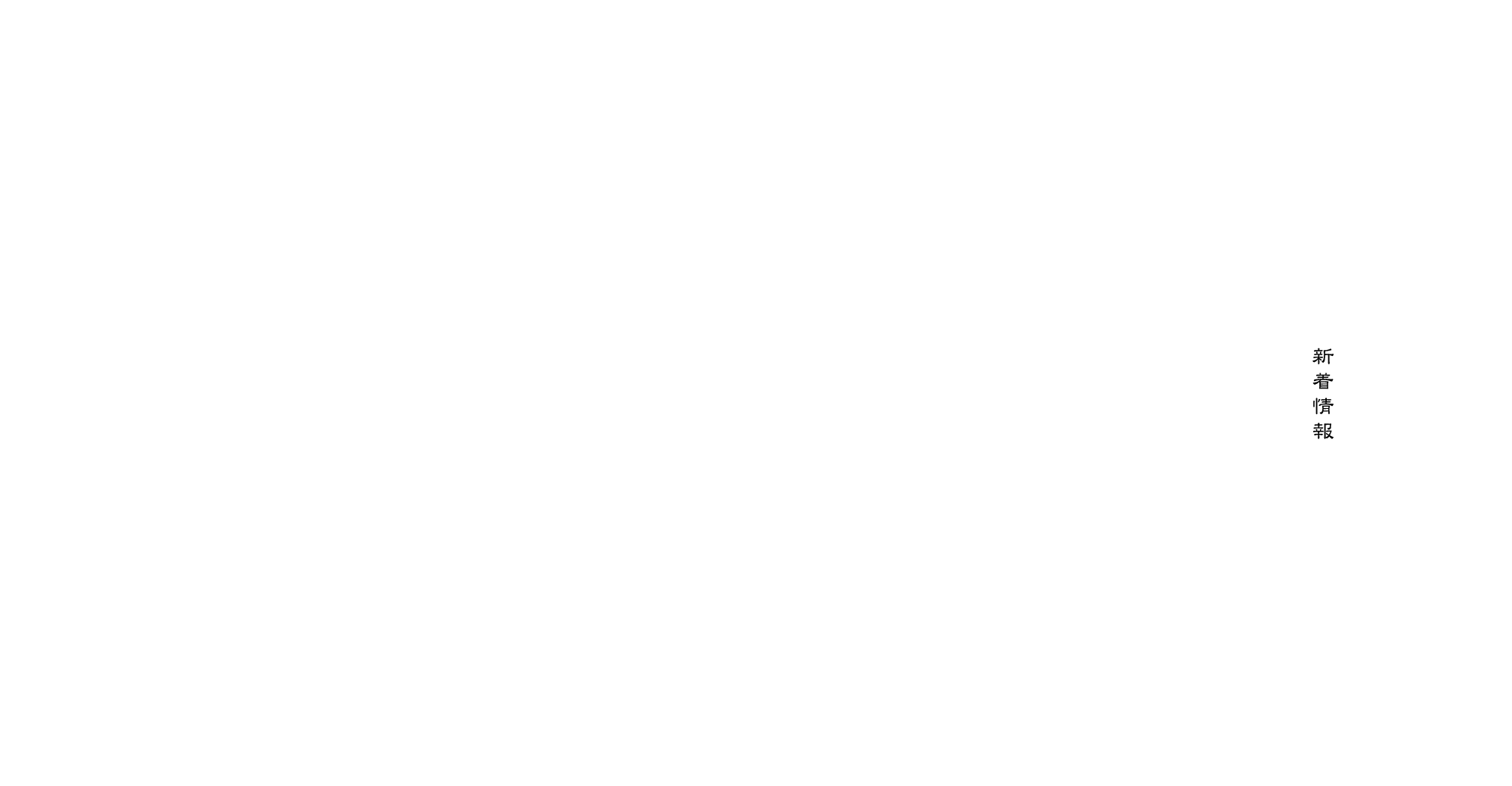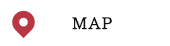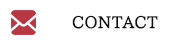皆さんこんにちは!
矢尾定の更新担当の中西です。
さて今回は
~だし・温度帯・時間差の科学 ~
仕出しは出来立て=最強ではありません。狙うのは**“食べ頃”の到着**。だしの落ち着き、酢締めのなじみ、煮物の味含ませがピークになる時計合わせが命です⌚。
1|春(弥生~卯月):香り立つ“初々しさ”
-
八寸:菜の花辛子浸し、桜鯛昆布締め、筍木の芽和え。
-
炊合せ:若竹煮(だし:一番だし7、薄口醤油1、味醂0.5、塩少々)。
-
寿司:手綱寿司(鯛×酢飯は弱めの合わせ酢で清澄感)。
→ 温度帯:常温寄り。木の芽・柚子の揮発を活かすため冷やし過ぎない。
2|夏(皐月~葉月):清涼と衛生のマネジメント ☀️
3|秋(長月~霜月):旨味の重奏
4|冬(師走~睦月):滋味と保温
5|献立表の“読みやすさ”と言葉選び
献立名は漢字+ひらがなで硬軟バランス。「炊き合わせ」「揚げびたし」「うぐいす醤油」など風景が浮かぶ語を。アレルゲン表示は枠外に明快、英訳は素材→調理法→味付けの順
6|数量・単価の設計
-
法要折詰:3,000~5,000円帯が主力。
-
お祝い会席箱:6,000~10,000円で器・紙質を格上げ。
-
大口(企業・学校):1,500~2,500円の“現場最適化”モデル(食べやすさ・片付けやすさ)。
7|まとめ
“時間差おいしさ”を設計できれば、仕出しは現地調理を超える瞬間があります。次回は**オペレーション(衛生・配送・設営)**を具体的に解剖します。
献立はこちら